今回紹介したいオージープランツは『ピメレア ピソディス“ウェディングベル”』
近年春に流通するオージープランツの中でも一際人気の高いピメレア ピソディス。
ただその性質や育て方についてはまだまだ謎に包まれており、手探りで育てている園芸家も多いのではないでしょうか。
特に夏越えが難しいというお話をよく耳にします。それもそのはず、ピメレア ピソディスは日本の環境とは大きく異なる西オーストラリア出身の植物です。
ピメレア ピソディスが好む環境を知り、育て方のコツを掴めばピメレア ピソディスを何年も育てることが可能です。
この記事では、『ピメレア ピソディス“ウェディングベル”』の特徴と育て方・成長記録を紹介しています。
ピメレア ピソディスの成長記録

当時4.5号サイズだったピメレア ピソディスを購入しました。
オージープランツブームの例に漏れず、ピメレア ピソディスも大人気のため苗を見つけるだけでも一苦労です。

お迎えした苗は1本立ちながらも、上部ではたくさんの花芽がぶら下がり豪華な見栄えです。
この花の姿形はまさに“ウェディングベル”そのもの。
ヤマモガシで溢れかえるわが家の庭に舞い降りた天使ことピメレアピソディス。
ただひたすらに可憐なこの花に癒される毎日でしたが、ある日強風でひっくり返ってしまい、一本立ちの幹の下の方でポッキリ折れてしまいました。
花後強剪定して仕立て直すつもりでいたので、前向きに考えてこの可愛らしいお花は切り花として部屋の中で楽しむことにします。
翌年春の様子

翌年の春は株立状に成長したそれぞれの枝が伸び、花芽も昨年とは比べ物にならないくらい多く付けてくれました。

可憐な花も健在。ピメレア ピソディスはどうしても下から見上げたくなりますね。
花の形状もさることながら、この色合い、黄色からピンクのグラデーションがまた美しいです。

ある程度花を堪能したあとは昨年同様にがっつり下の方で切り戻します。上の画像は切り戻してから4週間後の姿です。しっかり脇芽が生えてきましたね。
ピメレア ピソディスはそのままにしておくと枝がビロンビロンに長く育ってしまうため、毎年しっかり選定してコンパクトな樹形を維持しておきたいです。

カットした花は早速ドライフラワーに。退色してもある程度のところで色味は残るのでピメレア ピソディスの魅力は健在です。

ぶら下げて2週間ほど乾燥させると花が上向きで固まります。ぶら下がり形状ではないピメレア ピソディスを楽しむことができます。
ピメレア ピソディスの特徴とわが家の管理方法

| 学名 | Pimelea physodes |
| タイプ | |
| 原産地 | 西オーストラリア州南部 |
| 耐寒気温 | -5℃前後 |
| 開花期 | 2月〜5月 |
| 日照 | 日向むき |
ピメレア ピソディス“ウェディングベル”は西オーストラリア州の南部原産の珍しい低木です。
花は冬の終わりから春にかけて咲き、ベル型の大きな花をいくつも吊り下げるユニークな姿が特徴的。
花色はライムイエローからピンクや紫の入るとても珍しい色。1つの枝にいくつもの花をつけ、風に揺れる姿が可憐です。
お花の参考イメージ

開花期間も長く、型崩れしない状態で2ヶ月ほどは鑑賞できます。お庭で楽しんだあとは切り花にして、最後はドライフラワーで、花は1年を通して楽しめます。
開花期に合わせて苗の流通が始まるため、流通は1月〜4月の間と限られています。
育てる環境
わが家の栽培環境は千葉県の比較的温暖な地域で、夏の最高気温は38度、冬の最低気温は-3度ほど(年に1〜2回あるかないか)の環境で、北風の当たらない南向きの庭、もしくは軒下にて育てています。
わが家では、ピメレア ピソディスを午前中のみ日があたり、午後からやんわり日陰になる軒下スペースで育てています。
日当たりを好む植物なので、1日中日当たりの良い場所に置いても大丈夫ですが、ピメレア ピソディスは西オーストラリア出身の植物です。
西オーストラリアといえば夏の最高気温が30度前後で日差しが強く、湿度が低くいのが特徴。また、雨はほとんど降りません。そんな環境で育つ植物ですから、当然日本の夏の強すぎる日差しと蒸れが大の苦手です。
夏は庭の植木の陰で木漏れ日が当たるようなところに移動するか、遮光シートなどで強すぎる日差しを遮ってあげると安全です。もちろんわが家のように軒下管理でも◎
冬の寒さについては割と強く、温暖な地域であれば屋外で十分冬越し可能です。多少の霜にも耐えられますが、枝が細いので重い雪を被るとポッキリ折れてしまいます。
わが家のピメレア ピソディスは一度強風でひっくり返ってしまい、株元付近で幹がポッキリ折れてしまったことがあります。
葉っぱが数枚しか残らなかったため、このまま枯れてしまうかと思いましたが心配をよそに回復。翌年には二回り以上ボリュームも増えすくすくと成長を続けています。
用土
ピメレア ピソディスは深く砂質で水はけの良い土壌を好み、pHは5~6の弱酸性が適しています。
わが家では、硬質鹿沼土と硬質赤玉土の小粒をベースに、市販の培養土と軽石(パーライト、日向土)、ベラボンなどを配合した水捌けのいい土を使用。
余分な水分を溜め込まないようやや小さめの鉢で管理しています。
水やり
ピメレア ピソディスへの水やりは、土の表面がやんわり乾いたタイミング、もしくは鉢を持ち上げてみて少し軽くなったと感じたタイミングで与えています。
蒸れに弱いため、夏場は水切れに注意しつつも気持ち控えめに。この時期は雨には当てず、できれば人の手で水分コントロールができると失敗のリスクを大きく減らせます。
花芽をつけるのは寒い冬の時期なので、意外と冬の間も水を欲しがります。
肥料
ピメレア ピソディスの固形肥料には『両筑プランツショップ』で購入した、リン酸をほとんど含まない「グレヴィレア バンクシア専用肥料」を定期的に与えています。
この肥料はその名の通り「プロテオイド根」をもつバンクシアにも安心して与えることができる配合で作られています。
固形肥料のほか、春と秋には1週間に1度のペースで液肥とバイオスティミュラント活力剤を併用して与えています。
剪定
ピメレア ピソディスの剪定は花後、4月の半ば頃に全体の半分ほどの長さに切り戻しています。
ピメレア ピソディスは剪定に対する反応もよく、切り戻してから2週間ほどで葉の付け根から新芽がポツポツとふき出します。
そこから夏にかけて生育期になりぐんぐん伸びるため、花芽形成されるギリギリ前の晩夏に、もう一度切り戻すとコンパクトな樹形を維持したまま枝葉のボリュームを増やすことができます。
切り戻しはタイミングを間違うと翌年の花芽を落としてしまうため、なるべく夏前までには済ませておくと安心です。
ピメレア ピソディスを実際に育ててみた感想
夏越しが難しいと聞いていた割には難なく超えてくれました。ひたすら軒下管理だった事が功を奏した気がします。
成長速度も早く、剪定にもよく反応するため仕立てがいのある植物です。
冬から春に開花する花は開花期も長く、ドライフラワーになってもほとんど形状が崩れないため1年を通してこの可憐な花が楽しめます。
ピメレア ピソディスの好む環境を知り、夏は涼しく管理してあげていれば、育てやすい植物かなという印象です。
冬に庭を彩れる数少ないオージープランツですのでおすすめです。
















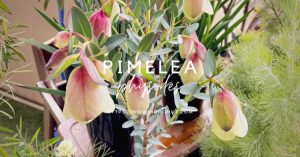
コメント